 HeliosMoon プロローグ
HeliosMoon プロローグ
小さな俺は、森の中にいた。
修練用のぼろぼろの剣を握りしめ、がたがたと震えていた。目の前に対峙していた恐ろしいモンスターは耳をつんざくような鳴き声をあげまばゆい光に包まれたかと思うと、"ひとりの人間"となって倒れていた。
「ウィン」
光の先には、剣を握った父親がいた。自分と同じ金髪の髪をかき上げ、額の汗を拭う。緑色の瞳で、我が子を厳しく見据える。
光の向こうにいた父。悲鳴とともに消えたモンスター。そして、そこに倒れている誰か。その人は、ぴくりとも動かない。
「・・・・・う・・・っ、うぇ・・・・ひっく・・・・・ぅ・・・う・・・・うぁぁ・・・・うわぁぁぁぁん」
身体の力が一気に抜け、握りしめていた剣を落とした。堰を切ったように溢れ出る涙は、助かったことへの安堵なのか。はたまた、父が人殺しをしたことへの恐怖なのか。子どもの自分にはこの感情を理解するだけの知識を持ち合わせていなかった。
泣きじゃくる息子の頭をくしゃりと撫でる。触れられると一瞬身体をびくっとさせ、泣き声は更に大きくなった。父は小さくため息を吐く。
「帰るぞ。・・・母さんが待ってる」
厳しい父親が、大嫌いだった。
今度はまた別の日だった。
小さな俺は、母さんに呼ばれて居間にいた。
「うわぁー・・・・すっげーきれい!!・・・これ、もらっていいの?」
母が差し出したブレスレットに視線を預けたまま訊ねた。赤みたいな、オレンジみたいな、綺麗な朱色に染まった革紐のブレスレット。シルバーの小さなプレートがキラキラしていて、とってもかっこいい。
「ええ。・・・これはね。ウィンが怪我したりしませんように、っていうお母さんのおまじないがかかっているの」
にこにことしている母が、そっと自分を抱き寄せる。やわらかな優しい匂い。自分とは違う、母の澄んだ青い瞳。さらさらと柔らかなブラウンの髪がくすぐったい。
「ウィンだけのお守りよ」
「ほんと!?」
ふたりでにっこりと笑いあう。ブレスレットの紐が自分の手首にはまだ大きすぎて、母が余ったところをしばってくれた。
「母ちゃん、ありがと!大事にする!!」
優しい母さんが、大好きだった。
少し大きくなった俺は、戦争に出兵する父親を見送ることになった。
「ほら、ウィン。不貞腐れてないで。お父さんにいってらっしゃいは?」
15歳にもなって、『いってらっしゃい』など。言えるはずがなかった。戦争へ赴く父とは、もしかしたらこれが最後かもしれない。顔を見ることが出来ない。
「もう、この子は・・・」
母が少し困り顔で言う。身長はもうすっかり母を追い越しているが、まだまだ子どもだった。父はその様子を静かに見、ゆっくりと口を開いた。
「・・・ウィン」
その口調は、これまでにないくらい穏やかだった。
「お前ももう大きいから、とやかくは言わない。父さんがいない間、母さんを頼んだぞ」
覚悟が入り交じった言葉は素直になれない自分を揺さぶる。父は続けた。
「ほら、これをやる。前から欲しがっていただろう?父さんの剣だ」
カチャリ、と古ぼけた鞘に入った見慣れた剣が差し出された。小さな頃、憧れてこっそり持ち出しては叱られていたあの剣。父の愛用の剣だった。大きくなり、父の厳しい稽古を受けた今の自分ならば十分扱えるということなのか。
「ッ、今更!!いらねーよ!!こんなの!!!」
ムキになって家の中へ飛び込んだ。力任せに扉を閉める。思った以上に大きな音がした。愛用の剣を息子に託してゆくなんて、父は死ににゆくと宣言しているようなものだ。身体の弱い母を置いて、なんて無責任な父親だろう。なにより、自分に母を守れるだけの力があるとも思えない。父への憤りと、父を越えられない自分への苛立ちが入り混じる。ひどく閉めた扉を背に、下唇を噛み締めた。
「・・・仕方ないな」
扉の向こうでため息混じりの父の声がした。
「行ってくるよ。ノエリア」
母に向けた、驚くほど優しい声。
「ええ、無事に・・・帰ってきてくださいね」
父に向けた、祈るようなやわらかな声。
その3年後のことだった。
ウィンが始めたばかりの傭兵の仕事に向かうある朝、母は持病の悪化により倒れた。父はまだ帰ってきていなかった。家計をひとりで支えてきた母を助けようと始めた仕事だったが、まだ大した稼ぎはない。ウィンは父の帰りを心から願った。母を元気にできるのは父しかいない。
母のために、がむしゃらに仕事を続けたウィンの剣の腕は少しずつ認められていった。仕事も軌道に乗り、やっと母の治療費をまかなえるほどになった。
「ただいま!母さん!!今日、リーナが晩飯作りにきてくれるってさ!!」
元気よく扉をあけて、真っ先に母の傍へ向かう。身体を起こした母が、ベッドの上で微笑んでいる。
「あら、そうなの。リーナちゃんに悪くないかしら」
「新しいメニュー作ったから試してほしいんだってさ!体に優しい料理だから、母さんにも感想ききたいんだって」
傭兵の仕事を請け負う酒場にはウィンと同年代の女の子がいる。酒場の看板娘のリーナは年齢が近いこともあり、ウィンにとって良き相談役であり理解者であった。
「最近仕事は、どう?」
気になる女の子が家に来るということで、張り切ってテーブルを拭くウィンの背中に母が訊ねた。
「あー、なんとなくコツが掴めてきた感じかな。始めはどうなるかと思ったけど、なんとかやってけそうだよ!」
手を止め、母のほうを見てニカッと笑う。
「ふふ、良かった。・・・最近、ウィン、昔のお父さんに似てきたわね」
母がそう微笑むとウィンは少しばつが悪そうな表情で、そんなことねーよ、と再びテーブルを拭きはじめた。
俺が二十歳のとき、唐突に、悲しみはほぼ同時にやってきた。
「・・・母さん。明日、父さん一緒に迎えにいこう」
その夜、戦地から届いた手紙に視線を落としたまま口を噤んでしまった母に言った。父が戦死した。迎えにいくといっても、遺体は残っておらず、遺留品が残っているらしい。母は喋らない。
「・・・母さん、だいじょう」
「ウィン」
母が顔をあげた。
「ごめんね。母さん大丈夫だから。明日、迎えにいきましょうね」
「・・・うん」
いつもの母だった。
遺留品の引き取り場所である首都のヘクトまではどう向かおうかウィンは考えた。ここ最近は体調が良い母だけれど、かなり距離がある。少し上等の馬車を頼もう。
次の日、母は目を覚まさなかった。
「母さん」
ああ、嫌だ。
「母さん、朝だよ」
ああ、嫌だ。
「母さん?」
いやだ。思い出したくない。
「ウィン・・・大丈夫?」
リーナが泣いてる。
「そうか・・・ウィルフレッドも・・・・残念だったな・・・」
酒場の爺さんがこんな顔するのを初めて見た。
声が出せなかった。目の前がぼやける。どうして。なんでこうなるんだよ。父さんが死んだってきいて、一緒に迎えにいこうって俺言ったじゃんか。なんで父さんが迎えにきてんだよ。なんでそっちから母さん迎えにくるんだよ。どうしたらいいんだよ。ひとりになっちまったよ。大好きな母さんもろくに守れないで、大嫌いな父さんに連れて行かれちまった。俺どうしたらいいんだよ。
どうしたら――。
「ウィン、いい子ね」「馬鹿、そうじゃない」
「ウィンはお父さんに似たから、きっと強くなれるわ」「ノエリアはお前を甘やかすから」
「ごめんね。ウィン」「何度言ったらわかるんだ」
「あ、ウィンいらっしゃい!今日は何食べてく?」
「おぉ、ウィン、来たか。お前さんに仕事の依頼がはいっとるぞ」
「気にくわねぇヤツだな」
「ずっと、ずっと捜していたのよ・・!!」「・・・・マ・・マ・・・・・・ママ・・・・・・・・・・ママぁっ!!」
「お前に会えて、本当に良かった」
「っ、ウィン――――――!!!!」
―――目が、覚めた。
朝だ。夢か。
いつもどおり枕が明後日の方向にすっ飛んでいる。
こんこんっとノックの音がした。
「ウィン、起きてるか?」
「お・・・おおう!」
「朝飯、冷めるから早く来るようにアンジェさんが。先に食べてるぞ」
平常どおりの、相棒、ロートスの声。先ほどの夢の最後の声は確かに相棒の声だったはず。しかし、それはこれまで聞いたことのない悲鳴のような声だった。
扉の向こうで階段を下りていく音が聞こえる。
ウィンは身体を起こした。枕を拾ってベッドに放り投げる。カーテンを開け、窓を開ける。気持ちのよい朝の空気が入り込んできた。
「んーーーーっ・・・・あー」
ぐぅっと腕を上げて伸びをする。身体を少しひねる。今日も健康だ。金髪の頭をガシガシと掻くと、小鳥のさえずる声が聞こえて、またいつものように一日が始まるのだと実感する。
そうだ、夢だったのだ。
懐かしい、夢をみた。
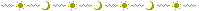
ウィン=モーニングとロートス=ドロップ――2人組の何でも屋「ヘリオスムーン」が稼業の拠点にしている「セラフィーナ」。酒場を兼ねる小さな宿屋だ。ヘクトの街の西に位置しており、客足はそれほどではないが、馴染みの客が多く雰囲気も良い。
この店の主人アンジェリカ=フォスターは元々シュレイニの出身で、シュレイニの酒場の息子と結婚し、10年ほど前にヘクトに移り住んだ。ウィンを小さい時からよく知っている気立ての良い女性である。その縁もあってか、ウィンたちは下宿させてもらいながらこの地で何でも屋の仕事をしている。
階段を元気に駆け下りると、そこはもう酒場のフロア。アンジェリカの作った朝食のいい匂いがする。
「おはよう、ウィン」
アンジェリカがウィンの朝食を持ってきた。
「おはよう、アンジェおばさん!」
ウィンは元気な声で応える。
「さあ、冷めないうちに。飲み物は?」
「ミルクで!あー!腹減った!!」
朝食といえばミルクは欠かせない。ウィンは椅子にドカッと着席すると、目の前の朝食の湯気に顔を突っ込み思い切り深呼吸した。フライドエッグにカリカリのベーコン。引き立て役のレタスとトマト。優しい匂いのコーンスープ。焼きたてのトーストに、今日はバターを落とそう。2枚目はスープにつけて食うのも良さそうだ。
「お前は・・・・朝っぱらから元気だな・・・」
朝食に目を輝かせるウィンの様子をみていたロートスが気怠そうに口を開いた。すでに朝食を終え、食後のコーヒーをすすっている。表情を隠す、男性にしては長めの黒髪と、普通にしていても相手を睨んでいるような鋭い切れ長の目は、沈着冷静な彼をより一層引き立てる。
「いつものことだろー?」
切れ長の目にも物怖じせずケラケラと返答する。アンジェリカがミルクの入ったコップを置くと、ウィンは軽快にサンキューとお礼を言った。
「なに、嬉しいことでもあったのかい?」
普段からウィンが元気なのは承知だが、今日は特別元気そうにみえる。アンジェリカが訊ねた。
「んー?嬉しいことっつーか・・・・あ、夢見た。今日」
「夢?」
「うん。なんか、小さい時の思い出っつーか、なんつーか・・・・」
一瞬、母の亡くなった日の情景がよぎる。
「嬉しいことっていうよりもあんまり嬉しくない思い出の方が多かったかな」
苦笑しつつ、トマトを口に放り込んだ。
「ウィンの小さい頃ねぇ・・・」
アンジェリカは知る限りのウィンの幼い頃を思い出す。彼の境遇は知っているが、幼少期の幸せな時期ももちろん知っていた。
一方、ウィンの過去を知らないロートスは少しからかうように、それでも静かに言う。
「意外だな。お前に嬉しくない思い出なんてあるのか」
「ってぇ、どーゆー意味だよ!!」
ロートスと出会って3年ほど。毎日元気いっぱいのウィンを傍でみていれば、そのような言葉が出てきてしまうのも当然かもしれない。昔から変わっていなさそうだがなと返すと、ロートスはコーヒーを一口。
「おいおいおいっ!それってぇ、つまり!昔っから嬉しい思い出ばっかりの人生楽しい事しかねぇみたいなヤツだってことか!?俺が!!!」
「わかっているじゃないか」
「だぁーーッ!!ひでぇ!!」
がったんと音を立ててウィンが立ち上がる。
「お前!!いくら俺が"お前より明るくて""人気ある"からってそれは偏見だ!へ・ん・け・んー!」
「・・・・さりげなくお前も酷いぞ。あと、指をさすな」
あっはははははは。ふたりのやりとりに、堪らずアンジェリカが噴き出した。
「笑うなーっ!俺は真剣なんだーっ!!!」
騒がしい。ひとしきり叫ぶと、ウィンは着席した。ふてぶてしくフライドエッグにフォークを突き立てる。すぐに、思い出したようにロートスを見やる。
「・・・じゃ、じゃあ、お前の方こそ、どうなんだよ?」
「どうって、何が」
「だから、昔の思い出だよ!」
「・・・・・無いな」
ウィンから視線を外し静かに答えた。
「えー、なんかあるだろー少しくらい」
フライドエッグがぼろぼろになっていく。ロートスはしつこい相棒を一瞥した。
「まぁ、無いこともない」
その言葉にぱぁっと目を輝かせるウィン。
「それじゃあ・・・!」
「ただ、お前に話す価値のある話かどうかと言われれば、無いな」
さらりと一蹴。ウィンが不服そうな顔をする。ベーコンの端っこをくわえると引き続きフライドエッグをぼろぼろにしはじめた。
「ロートスがいじめる」
「あんまり人の過去詮索すると、女の子に嫌われるよ」
「それとこれとは関係ねぇ!!!」
アンジェリカがウィンをからかう。拍子に、ウィンの口から吹っ飛んだベーコンがウィンのコーンスープにダイブしていた。
カランカラン。
「おはようございまーす!」
ウィンがベーコンをすくっていると、通りに面した扉が開き、元気な男の子の声が響いた。セラフィーナに通っている情報屋、ガッド=スニーカーである。橙色のバンダナの隙間からシルバーのさらさらした髪がのぞいている。見た目にも元気な印象の少年だ。
「あら、ガッド。いらっしゃい」
「アンジェおばさんおはようございます!チーズトーストお願いします!」
アンジェリカに向かってにこにこと挨拶すると、ガッドはいつものように好物のチーズトーストを注文する。
はいはい、と答えたアンジェリカがカウンターの奥へ消えていった。
「よぉ、ガッド!」
救出したベーコンを咀嚼しながらガッドに向けて片手を挙げるウィン。
「ウィンさん、ロートスさん!おはようございます。本日はどちらへお仕事で?」
つぶらな赤みを帯びた瞳をキラキラさせて、ふたりに駆け寄ってきた。
「いや、今日はまだ予定は入っていない」
「なんかいい仕事あんの?」
ウィンがバターの染み込んだトーストをかじる。
「はい!いろいろありますよー!」
ふたりの言葉を聞くと、ガッドは肩かけ鞄から意気揚々と青いノートを取り出した。
ウィンとロートスは人々から"依頼"を受けて仕事をし、収入を得る。その依頼を収集してくるのが、ガッドのような情報屋の仕事である。情報屋は街の通信局、または各々のお得意様から直接依頼の情報を仕入れる。それらの情報をウィンたちのような何でも屋や傭兵などに売り、生計を立てるのだ。
「えっとですねぇ・・・」
青いノートをぱらぱらとめくっていく。一昨日会った時点では黄色いノートを使っていたことから、ガッドが情報を得ることに関してそれなりの能力を持っていることがわかる。ページをめくる手が止まった。
「あ、これは隣町ですね。バーバラというおばあさんからの依頼で」
「却下」
「え!?」
バーバラという名前を聞いたロートスは即座に拒否の姿勢を示した。ウィンとガッドが意外そうな声をあげるが、ロートスは答える。
「飼い猫のピーターを捜してほしい、だろう?」
「おぉ、お見事」
ガッドはぱちぱちと手を叩いた。ロートスはため息を吐く。
「1週間前に請け負ったばかりだろう。またいなくなったのか、あの猫は」
隣町のテクナに住むバーバラというおばあさんは、ガッドのお得意様でもあった。ガッドを孫のように可愛がりながら、何かあればすぐガッドに連絡が来る。1週間前、猫のピーターはバーバラさん宅の隣の家で日向ぼっこをしているところを保護したばかりだった。その2週間前は、テクナ港の船乗りたちに魚をもらっているところを発見した。そのまた前は、と遡ればキリがない。
ウィンが堪らず立ち上がる。
「愛が無いなロートス!愛が無い!!何度でも捜してやろうぜ!?あのばーさん、1年前にじーさん亡くして寂しいんだよ!」
「1年前から月2回も同じ依頼されてお前はどうも思わんのか」
「思わん!!」
「ガッド、次」
さらっと流された。
「えっとですねー・・・これは少し遠いですが、ロナベル自治区ってご存知ですか?」
「あぁ、反戦グループが戦争から逃れるために作った町・・・であっていたよな?」
「はい、その通りです」
ヘクトから南西に向かった場所にある町、ロナベル自治区。戦争に反対する人々が抗争から避けるため、10年前に作られた町である。
「そのロナベルに幽霊が出没するという情報が入りましてね」
「っ、はぁ!?幽霊!!?」
「・・・この精神体のはびこるご時世に、幽霊?」
ロートスが疑わしい眼差しを向ける。
「えぇ。もしかしたら、幽霊ではない他の何かかもしれません」
首をかしげたガッドが顔を顰めた。
「ただ、町に住む子どもたちがひどく怖がっているという話も聞きますし、気になって」
「ふむ・・・ガセの可能性は?」
ロートスに問われ、更に悩ましい表情をするガッド。
「うーん・・正直わかりません。自治区には魔法術士がいないので、通信局に参加していないんです。だから、通信局の情報ではないので、信憑性が薄いんですよね。自治区から定期的に情報員が派遣されていますが、新しい情報とは限りませんし、自分で見て確かめるしか手段がありません」
「なるほどねぇ・・・」
ウィンが指についたパン屑を払いながら唸った。争いから逃れるために作られた町には戦争の原因とされている魔法術士の居住を禁止しているため、魔法利用をする施設が存在しない。情報員がヘクトに訪れるのは週に一度だけであるから、情報の鮮度はどうしても落ちてしまう。
「猫さがしよりは手ごたえがありそうだが、ガセだったら無駄足だ」
顎に手を添え、呟く。
「そうなんですよね。こちらも情報屋としてはガセ情報を掴ませるわけにはいきませんので、この辺はお二人の判断で」
「うーん、どーする?」
ウィンがロートスを見た。
「他を聞いて判断しよう」
「わかりました。では・・・」
ガッドはノートをめくりながら様々な依頼内容を読み上げていった。
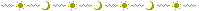
「以上です。どうしますか?」
ぱたんとノートを閉じるガッド。ロートスはため息をついた。
「どうした?ロートス」
「シュレイニにいた時の方がまだまともな仕事が来たものだったが・・・なんだこれは」
元々、危険な仕事ばかりをこなしてきたロートスが呆れるのも無理はない。猫さがしや買い物の間の子供の世話、しいていうなら一番危険な物置小屋の屋根の穴の修理など、呆気にとられる依頼の数々。
「いいじゃねぇか、頼られて」
言葉が見つからない、といった様子でロートスは髪をかきあげ難しい顔。反面、ウィンはとても嬉しそうな表情だった。
「ウィン、お前はどうも思わんのか」
「思わん」
正直な答え。ロートスはウィンの回答と表情を見、もう一度深くため息をつくと、コーヒーを飲み干した。
「・・・・勝手に決めろ。どの依頼を請け負うか」
「え、いいの?」
「お前の好きなようにしろ」
コイツにはついていけない。そんな調子にも聞こえる言い方ではあるが、信頼しているからこその言葉でもある。どうしますか、とガッドがウィンに訊ねる。じゃあ、とウィンが続けた。
「全部」
「は!!?」
ロートスが珍しく声をあげる。
「ぜ、全部って・・・・今言ったの全部ですか!?」
「おう!」
力強く返事をする。すかさずロートスが口を挟む。
「俺たちじゃなくても出来る依頼ばかりだぞ、ウィン」
少しは物を考えてから言え、と。
「考えてるって!俺なりに!シュレイニにいた時は傭兵だったから、戦うような依頼ばっかり請け負ってきた。でも、俺、1つだけに捉われるのって、なんか勿体ない気がするんだよな。だから、何でも屋なんだろ、俺たち」
真っ直ぐな瞳が、訴える。
「・・・それはそうだが」
「ただトップを目指すだけが傭兵じゃない。ただ納得のいく仕事だけを請け負っているだけじゃ、何でも屋なんて言えねぇんだよ」
ふざけているように見えて、ウィンは一本揺るがない信念をもって生きている。ロートスはわかっていた。コイツは馬鹿だ。馬鹿正直な彼が羨ましかった。
「ふっ」
堪らずロートスは小さく笑うと、ガッドに見えるように指を3本立てた。
「ガッド、情報料はこれでどうだ?」
「え、ロートスさん、ホントに全部請け負う気ですか!?」
「あぁ」
ウィンが嬉しそうににやっと笑った。
「・・・そうですか。じゃあ、僕は止めません。・・・・けど」
言葉を濁すガッド。
「情報料もう少し♪」
「そうきたか」
少年といえど、立派な商売人である。いたずらっぽい表情で、2人にねだる。
「僕だって生活かかってるんです!情報全部いただかれるのなら、僕もそれなりにいただかないと!」
「3枚で勘弁しろよー」
ウィンも負けじと食い下がる。そこへアンジェリカがチーズトーストを持って現れた。
「なんだか賑やかだねぇ。次の仕事、決まったのかい?はい、ガッド、チーズトーストお待たせ」
香ばしいチーズの匂いに包まれる。
「あ、ありがとうございます!」
ぱぁっとガッドはいっそう目を輝かせた。すかさずロートスが入る。
「じゃあ、そうだな。情報料は銀貨3枚と、そのチーズトーストの代金。プラスしてバーバラさんのアップルパイでどうだ?」
あまり笑顔を見せないロートスが少しだけ口角をあげた。大好物のチーズトーストをお金を払わずに楽しめる。そして甘いものが大好きなガッドにとって、それは魅力的すぎる提案だった。
「・・・ロートスさん」
ロートスを見るガッド。ロートスの表情が物語る。
「わかりました。なかなか商売上手で。毎度あり♪」
「お前もな」
ガッドがにっこり笑ってチーズトーストにかぶりつくと、ロートスも少しだけ微笑んだ。よおし、今日も忙しくなるな!とウィンがミルクを一気に飲み始める。
「そういえば、ウィン」
アンジェリカが口を開いた。
「あん?」
ミルクが中途半端に残っている。アンジェリカが続ける。
「アンタ、いつも腕にしてる朱色(あかいろ)のブレスレットはどうしたんだい?」
朱色のブレスレット。夢にも出てきた、嬉しい思い出。母さんにもらったブレスレットのことだ。あの日もらってからずっと肌身離さず身につけてきた。もちろん、今日だって左腕に。
「・・・・・あぁぁーーーーー!?」
無かった。
「ちょ、なんでないんだよ、え!!!?はずしたりなんかしねぇのに!!!!?」
コップを乱暴に置くと、椅子が転げたのも気にかけず、がったんがったん階段を駆け上がっていった。上の階からバタバタ音が響く。
「なんか・・・大切なものなんですかね?」
「あの様子だとそんな感じみたいだねぇ・・・」
「恋人から貰ったとか?」
ガッドの発言にアンジェリカとロートスが笑う。
「ウィンがかい??」
「さぁ、知らんな」
そう言っているうちに、静かになった。
「あ、とまった」
「・・・見つかったのか?」
ロートスは立ち上がると、様子を見に階段を上がる。セラフィーナの2階には、宿として使われている部屋が4部屋。そのうち奥の2部屋をウィンたちが借りている。廊下を進み、奥の右手の扉を開いた。そこには、大事そうにブレスレットの紐を縛り直すウィン。
「ウィン、あったのか?」
「寝てる間にヒモが切れたみたいだ・・・ベッドの下に落ちてた」
「そうか」
お前は寝相が悪いからな、と言おうと思ったが、やめた。開け放たれた窓から、チチチと、小鳥の声が聞こえる。
「それは、」
少しの沈黙を破るように、ロートスが続けた。
「お前の大切なものなのか?」
「ん?・・・・あぁ」
ロートスをちらりと見、空の向こうを見るウィン。
「母さんに貰ったお守りだ」
少し誇らしげに言った。
「そうか」
そよ風が入り込み、ふわりとカーテンを揺らす。
「今朝見た夢の、嬉しかった思い出なのか?それは」
ロートスの顔を見ていないが、とても穏やかな声だと感じた。
「そうさ」
ウィンの顔が見えていないが、とても嬉しそうな声だと感じた。
「・・・ふっ、そうか」
少し笑って、ロートスが踵を返すと、
「ロートス」
ウィンが名を呼んだ。
ウィンにはひとつ気になっていたことがあった。今朝の夢。悲鳴にも似た、相棒の声。少し嫌な予感がしていた。何故、急に昔の夢なんかを見たのだろう。そして、あの声は。ロートスは立ち止まったまま待ってくれている。
ロートスは普段とできるだけ変わらない調子で言った。
「・・・・スケジュールがいっぱいだ。出発するぞ」
「・・・おう!」
相棒の気遣いを感じとる。ウィンが普段とできるだけ変わらない調子で返事をすると、ロートスが立ち去っていく音が聞こえた。
――懐かしい、夢を見た。
「大事にする、か。大事にしすぎたから切れちまったのかな」
苦笑しながら、縛った紐が解けないかどうか、念入りに確認する。朱色はもらったときよりもすっかりくすんでしまった。
「これでよし。・・・っと、剣は」
ベッドのサイドデスクに立てかけられた剣を持ち上げた。一度は拒んだ、父さんの剣だった。少し眺めてから腰のベルトに固定する。しっかりと固定されたのを確認すると、ウィンは空を見た。雲ひとつない晴れた空。絶好の仕事日和だ。
「俺・・・」
誰もいない向こうの誰かに、話しかけるように呟く。
「元気にやってるよ」
父さん。母さん。
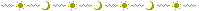
準備を終え、階段を下りると食べ終えた食器が片付けられていた。中途半端に残ったミルクのコップだけ残されている。
「もう行くのかい?」
支度を終えた様子を見て、アンジェリカが言った。ウィンがミルクを飲み干す。
「うん。仕事いっぱいあるからな♪」
「アンジェさん、ガッドのトースト代」
ガッドからの情報料として約束した、チーズトーストの代金をロートスは手渡した。
「・・・ん?ロートス?」
「いいんだ」
アンジェリカが何かを訴えたげに言ったが、ロートスが制止するのでそのまま受け取る。
「そうかい、ありがとう」
にこにこと満足げに見ているガッド。
「えへへ、ごちそうさまです!あ、ロートスさん、依頼のリスト渡しておきますね」
「あぁ、すまない」
ノートとは別に用意した、依頼の場所や依頼主などのメモ書きが渡された。
「へぇ、今回の仕事はそんなに多いのかい?」
普段メモ書きなどが用意されることはほとんどなかった。アンジェリカはいつもと様子が違うことに気付く。
「はい!」
ガッドがにっこり笑って続けた。
「僕の持ってきた情報全部ですから!」
「はぁ!?全部!?」
アンジェリカが声をあげるのを合図に、ウィンが腕を高々とかかげる。
「『人さがしから物さがし、モンスター退治からネズミ退治、子供の世話から寂しい夜のお供まで、どんな仕事も引き受けます、何でも屋・ヘリオスムーン』!」
何でも屋の結成当初、ウィンが徹夜で考えたセールス文句。今日は噛まずにすらすら言えたので、調子がいい。
「・・・ということだ」
「はぁ。なるほどね、お前たちらしいよ」
笑い混じりについたため息は、彼らを認めている証拠だ。
「へへっ、じゃ、行ってくる!」
真っ先にウィンが元気よく扉をあけて出て行った。ロートスは2人に小さく頭を下げて後を追う。
「お気をつけてー!!」
ガッドは出て行ったふたりの姿に向かって大きく手を振った。本日分の情報はもう出払ってしまったから、今日はもうガッドの仕事はない。
「・・・さて、と」
ふたりの姿が見えなくなったのを確認し、アンジェリカは室内に戻ろうとして、立ち止まった。
「そうだ、ガッド。あたしお手製のドーナツでも食べていくかい?特製ココア付き」
ふいに提示された魅力的なメニューにガッドは目を輝やかせた。
「はい!!あ、でも」
すぐに難しい顔をして、ぶつぶつと呟き出す。
「僕そこまで余分なお金は・・・あ、チーズトーストのお金払ってないからそれでいいのか・・・」
それを見てアンジェリカがくすりと笑う。
「今日は何も払わなくていいよ」
「え、どうしてですか!?」
室内に戻っていくアンジェリカについていく。今日は、何かある日なのだろうか。何かの記念日?少しだけ思考をめぐらすが、わからなかった。
「ほら、ロートスからもらった代金」
「・・・あ!これ!」
手を広げて見せてくれたそこには、銀貨が2枚。ガッド自身も、情報料としてすでに3枚受け取っていたのに。
「チーズトーストが3皿は食べれるね」
あははは、とアンジェリカがおおらかに笑った。
「午前中に雑用はすべて片付ける」
「げっ、マジで」
ガッドにもらったリストを見直してロートスが言った。
「そうでないとロナベルまで行けないだろう。向こうでは調査も必要だろうし、時間がない」
ウィンはわざと落胆したような表情と仕草を見せるがロートスは気にも留めない。
「手分けする。こちらがウィンの担当だ」
「へーい」
よく見るとテクナ方面の依頼がほぼ全部ウィンの手元に来ていた。走らないと間に合いそうにない。
「終わったら時計塔に集合だ。じゃあな」
「はいよ!」
今日も『ヘリオスムーン』の一日がはじまる。
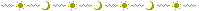
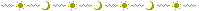

- Copyright (C) 2012 アカツキの家 -